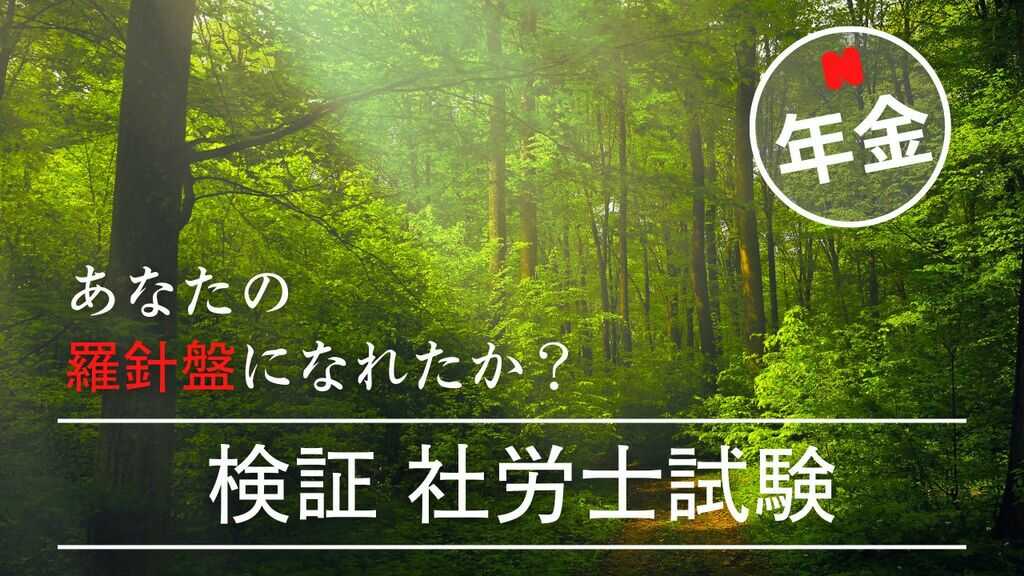社労士試験の受験生に向けて「貴方の羅針盤になりたい!」と始めたこのブログ、試験問題2024と照合してみることとします。
公正を期するため、試験後の投稿・追記等はこの検証に関する投稿が初めてであることを宣言しておきます。
検証:国民年金 選択式
【問題】 〈注意〉解答挿入済み
3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、・・・死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の<⑯配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹>であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:受給資格者(遺族年金)
ハ(配)コ(子)フ(父母)マ(孫)ソ(祖父母)キョウ(兄弟姉妹)
〈結果は・・・〉サンシン(三親)
【考察】
選択肢中から、親族の範囲が一番広いものを選べば正解でしたが、未支給年金の場合のプラス(三親等内親族)が含まれていたら、迷ってしまったかもしれません。
検証:国民年金 択一式 〔問1〕
【問題】
A 被保険者は、出産の予定日(・・・)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:産前産後 保険料免除(国民年金)
3,000(産前)円 イチゴー(1号=1500) サイフは(H31.2/1)免除!
【考察】
語呂合わせは、問題の論旨から外れていますが、解説の中でイメージの考え方を示しています。
産前産後の期間は、次のように捉えましょう!
・出産月の前月から4ヶ月間 「産前/産後」をそのままイメージ
「前」「産」「後」「後」
・(多胎妊娠の場合は)出産月の3ヶ月前から6ヶ月間 「産前産後」の前に「産前」を付けるイメージ 〔産前産前/産後〕
「前」「前」「前」「産」「後」「後」
検証:国民年金 択一式 〔問2〕
【問題】 ※部分は加筆
イ 国民年金法第30条の4の規定(※20歳前傷病)による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、・・・、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:20歳前障害基礎年金
20歳前と トーク(10-9) シナジー効果 皆霊視
20歳前と トーク(Talk) シナジー効果 皆レーシック(手術)
【考察】
前年と同じ論点が問われていませんか? (実際に上記は昨年度の投稿からコピーしました。)
全部または2分の1の支給停止が問題あると考えるなら、試験問題中で何度もアピールするのではなく、実際に3分の1へ支給停止を緩和する法改正をすればいいのに・・・!
【問題】
ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、・・・、あるいは初診日が令和8年4月1日前にある時は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(・・・)に保険料の未納期間がない者である。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:厚生年金 保険料納付要件(特例) 2021
ハサミ(令和8年3月未日) で チョッキン(直近) 婿(65歳)
【考察】
原則よりも、特例に注意です。この特例は適用日が更新され続ける、珍しいケースです。
検証:国民年金 択一式 〔問3〕
【問題】
D 積立金の運用は、・・・、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:年金積立金
最近(財金)酔った?(預託) 熱か?(年積管)帰宅!(寄託)
【考察】
2020年に投稿した語呂合わせですが、今でも出題されるんだ! という驚きと共に、今後もGPIFの運用成果からは目を離せません!
預託と寄託の漢字テストです!
検証:国民年金 択一式 〔問5〕
【問題】
D 第1号被保険者が・・・産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、・・・、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:産前産後 保険料免除(国民年金)
3,000(産前)円 イチゴー(1号=1500) サイフは(H31.2/1)免除!
【考察】
語呂合わせは、問題の論旨から外れていますが、解説の中で説明しています。
【解説】
国民年金第1号被保険者の出産(H31年2月1日以降)の際、産前産後の国民年金保険料を免除
効果として保険料納付したものとして年金受給額に反映するのが、他の免除規定との違いです。
付加保険料も納付できることも押さえましょう。
検証:国民年金 択一式 〔問7〕
【問題】
エ 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
【投稿】
年金:特例的な繰下げみなし増額制度 2023法改正
腰(5年4月)に 縄(70) 徳利下げ(特例的な繰下げ)
【考察】
時効5年で年金をもらえなくなる期間が発生しない為の救済措置です。
【問題】 〈注意〉誤りの問題です
オ 老齢基礎年金の・・・未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:受給資格者(遺族年金)
ハ(配)コ(子)フ(父母)マ(孫)ソ(祖父母)キョウ(兄弟姉妹)
〈結果は・・・〉サンシン(三親)
【考察】
「選択式」と同じ論点です。 『1つの語呂合わせで2度おいしい!』
検証:国民年金 択一式 〔問8〕
【問題】
ウ 付加保険料の納付は、・・・産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
【投稿】
【社労士試験の記憶術】年金:産前産後 保険料免除(国民年金)
3,000(産前)円 イチゴー(1号=1500) サイフは(H31.2/1)免除!
【考察】 ※[問5]D と同じ論点です!
語呂合わせは、問題の論旨から外れていますが、解説の中で説明しています。
【解説】 ※[問5]D と同じ論点です!
国民年金第1号被保険者の出産(H31年2月1日以降)の際、産前産後の国民年金保険料を免除
効果として保険料納付したものとして年金受給額に反映するのが、他の免除規定との違いです。
付加保険料も納付できることも押さえましょう。
検証:国民年金 択一式 〔問10〕
【問題】 〈注意〉誤りの問題です
C 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての〔要約:半額免除期間-48月、1/4免除期間-12月〕・・・死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
【投稿】
【【社労士試験の記憶術】年金:死亡一時金
最後(サイゴ)は12万 ニコニコ GO! GO! GO!
フカヒレ8,500円
【考察】
本人納付として算定された期間が最低ラインの3年に満たないことで解答できます。
3年から40年まで語呂合わせで、どの期間が出題されても解答できます。
付加保険料を納付していた際の死亡一時金の加算8,500円も、定例的に出題されるので覚えておきましょう!